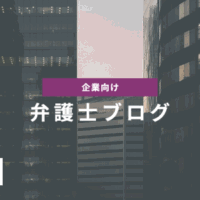今回は、労務管理についての連載企画第4回目となります。前回まで、労働時間制度を紹介してきましたが、今回は休日・休暇制度について説明します。年末年始は連休としている会社も多いと思いますので、この時期に休日や休暇の設定、そして管理について考えていただければと思います。
1 休日と休暇の違い
⑴ 「休日」と「休暇」はどちらも休みのことですが、「休日」は法律上そもそも労働義務が課されない日のことを指します。そして休日には
- 法定休日
- 法定外休日
の2種類があります。
まず、法定休日は労働基準法35条で「毎週少なくとも1回」(同1項)または「4週間を通じ4日以上」(同2項。変形週休制)と定められているものです。法定休日は、労働基準法が定めた最低ラインの休日日数であり、これより休日を少なくすることはできず、違反した場合は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される場合があります(労働基準法119条1号)。毎週少なくとも1日の休日を与える場合には連続勤務は最大12日までということになりますが、変形週休制の場合は連続勤務を最大24日までさせることができるため、労働者の過労に繋がる恐れが指摘されています。そのため、変形週休制を「2週間を通じて2日以上」に変更して連続勤務の上限を13日とする方向で法改正が議論されています。
次に、法定外休日とは、法定休日以外の休日のことで、会社が任意に設定する休日のことです。ただ、任意といっても必然的に法定外休日を定める必要が生じる場合もあります。つまり、労働基準法では1日8時間・1週間40時間という労働時間の原則が定められていますが、1日フルで8時間の労働をさせる場合、労働日は週5日となり、必然的に残り2日は休日にしなければならなくなります。そのため、法定休日1日と法定外休日1日を定める必要があり、多くの会社では週休2日制(この場合、年間休日は104日になります。)が採用されている仕組みです(例えば、1日の労働時間を6時間に設定すると、労働日を週6日にしても週36時間の労働時間になるため、法定休日1日のみでも良いということになります)。
なお、法定休日と法定外休日は土日に設定している会社も多いですが、これは法律上の義務ではありません。そのため月曜日や火曜日を休日として定め、土日を労働日として設定しても全く問題はありません。また、休日に労働させることもできなくはないですが、その場合は必ず36協定を締結して労基署に届出なければならず、休日出勤には休日手当や割増賃金の支払いをしたうえで、代休を設けなくてはならないため注意が必要です。
⑵ 「休暇」とは労働義務を負っているが休んでもいい日のことを指します。そして、この休暇も
- 法定休暇
- 法定外休暇
の2種類があります。
まず、法定休暇には、年次有給休暇(労働基準法39条)、産前産後休業(同法65条)、生理休暇(同法68条)、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇(以上、育児・介護休業法)があります。これらは、法律によって当然に認められた労働者の権利ですので、要件を満たした申請があれば会社は休暇として認めなければなりません。
一方、法定外休暇とは、会社が独自に定めているもので慶弔休暇、リフレッシュ休暇、誕生日休暇、アニバーサリー休暇(結婚記念日や子供の誕生日など)等があるようです。最近は、災害時のボランティア活動等が活発化したことに伴い、ボランティア休暇を設けている会社も見かけるようになりました。法律上、設定が義務付けられているものではありませんので、名称・条件・日数は千差万別です。有給か無給かも会社が就業規則で定めることで自由に設定できます。
⑶ では、年末年始の休みは、会社でどのように位置付けられるでしょうか。
以上のとおり、法律上定められたものではありませんので、法定外休日または法定外休暇のいずれ かになりますが、休日としてしまった場合には出勤させる場合に条件や負担が生じてしまうため、どこの会社も法定外休暇として定めることになるかと思います。「法定外休暇」ということは、いつからいつまで年末年始の休みにするのか、有給か無給か、そもそも年末年始の休みを設けるかということ自体も会社の自由です。つまり、年末年始の休みを法定外休暇として設けず、「年末年始にまとまって休みを取りたい場合は年次有給休暇を使って」としても違法ではないということになります。
2 年次有給休暇取得の義務化
⑴ 年次有給休暇については、2019年4月の改正労働基準法施行により、年10日以上付与されている労働者に対して、最低でも5日の有休を時季を指定して取得させることが全ての会社に義務付けられました(労働基準法39条7項・8項)。それまでは「労働者の権利」であった年次有給休暇が、「使用者の義務」という位置づけにもなったといえます。つまり、これまでは、年次有給休暇の残日数があっても取得しないという従業員もいたでしょうし、会社としてはそれならそれでよかったと思いますが、法改正後は、会社が主導的に従業員に年次有給休暇を使わせて休ませなければいけなくなったということです。
この「年10日以上付与される労働者」とは、6か月以上勤務していて8割以上出勤している従業員が対象となります。例えば、4月1日入社の従業員(有期雇用・無期雇用を問わない)は、10月1日から翌年の9月30日までの1年間で年次有給休暇を10日間取得できるということです。具体的な付与日数は、次の表のとおりです。
| 勤続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇は取得する理由は何でもよいとされています。そのため、労働者からの年次有給休暇の請求にあたって、取得理由を会社に説明しなければならない義務はありませんし、理由次第で請求を認めない、ということも許されません。また、年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないとされていますので(労働基準法39条5項)、労働者が具体的な月日を指定した場合には、「時季変更権」による場合を除き、使用者は従う必要があります。
※「時季変更権」とは、労働者による年次有給休暇の申請にあたって「業務の正常な運営を妨げる場 合」に限って他の時季に与えることができる(労働基準法39条5項ただし書)とされているものです。会社としては、同一期間に多数の労働者が休暇を希望しているため、事業運営が成り立たない場合等は、この時季変更権を行使するということも考えられるでしょう。
⑵ 年次有給休暇取得が義務化された、といっても、労働者が自主的に5日以上の年休を使うのであれば、会社としては時季指定をする必要は特にありません。そのため、まずは、労働者が自主的に年5日以上の年次有給休暇を取得するように会社から促すことが重要です。
例えば、給与明細書の中に年次有給休暇の残日数と基準日から1年間の取得状況を記載しておき、労働者に対して年次有給休暇の日数を知らせることが考えられます。それでも労働者からの自主的な年次有給休暇の請求が少ない場合、例えば基準日から半年が経過した時点で、3日以上の年次有給休暇を取得していない従業員にアラートや管理職からの取得奨励をする、という対策も良いと思います。
もちろん、その前提として、年次有給休暇を取得しやすい職場環境作りも重要です。いくら使用者や管理職が取得を促したところで、慢性的な人員不足等により年次有給休暇を取得しづらい職場環境であれば、かえって従業員の負担となりかねません。また、使用者としては、部署ごとや年代ごとに、年次有給休暇の取得率や傾向を把握しておくと、管理の助けになりますし取得推奨もしやすいでしょう。
アラートや管理職からの取得奨励でも労働者が年次有給休暇を取得しない場合には、労働者との面談や意見聴取を行った上で、会社から年次有給休暇の時季を指定して取得させるということになります(が、上記のような取得しやすい職場環境作りをしておけば、時季指定まで行う必要がない、となる会社も多いのではないでしょうか)。
また、年5日取得させる義務を果たすために、労働組合(又は過半数代表者)との間で労使協定を締結し、年次有給休暇の計画的付与制度を導入することを検討しても良いと思います。例えば、夏季や年末年始に年次有給休暇を計画的に付与して大型連休にすることや、休日の中日に年次有給休暇を付与して4連休や5連休にする、等が考えられます。
以上、今回は、休日と休暇の違い、そして2019年4月から始まった年次有給休暇の取得義務化について説明しました。
2019年4月から始まった年次有給休暇取得の義務化ですが、社内規定等の制度が整っていない会社が多い印象を受けています。取得義務を果たしていない場合、まずは労基署の監督・指導の対象となり、改善されなければ罰則(労働者1人あたり30万円以下の罰金)が科されるようになっていますので、注意が必要です。
また何より、近年は「ブラック企業」という言葉もあるように、労働者から見た企業イメージを整えることが従業員のモチベーション維持や人材の定着にかかわってくる時代ですので、このあたりはクリーンな経営を目指していきたいものです。
休日や休暇制度の設定や年次有給休暇の取得義務化への対応状況について、自社の運用が法律上問題ないのか、見直しの必要はないのか等をお考えの方は、ぜひ、ニューポート法律事務所にお気軽にご相談ください。